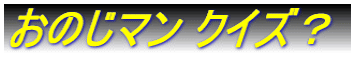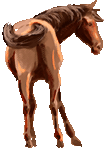
「馬に乗ってみたい」 (平成14年)
馬で思い出すことは、小学生のころ、山の学校の通学路を町の役場に通う隣村の人が、馬に乗って駆けてくる姿です。ひずめの音が聞こえてくると、馬にはねられないようにと、道の端によけてちぢこまっていたものです。怖かったという思い出とともに、かっこうよかったなぁという、あの乗馬姿にあこがれる気持ちがあります。駒音高くとか、馬を駆るという言葉なんかにしびれます。人生そのものも、威風堂々と歩みたいものですね。
「馬車馬の如く」「馬の耳に念仏」「馬耳東風」など悪い意味合いに遣うことが多いのですが、「馬と猿」は仲のよいことのたとえ。「馬には乗ってみよ、人には添うてみよ」は人柄のよしあしもいっしょに暮らしてみなくてはわからない、
という意味だそうです。最後に今年一年、うまい話には気をつけましょう。そして、ウマのあう友と良き人生を願います。
12子の半分まできました。午は「正午、子午線」の午であること知っていましたか?
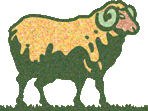 「羊と美・養・翔・善」(平成15年)
「羊と美・養・翔・善」(平成15年)羊でで思い出すのは「羊頭狗肉」「羊が一匹、羊が二匹・・・」「ひつじぐも」でしょうか。
「羊頭狗肉」は、羊の頭を看板に出して、実は犬の肉を売ることからきた故事成語で、名と実が一致しないことを言います。このことから推測できるのは、昔は犬の肉を食用にしていたということ、そして、羊の肉は美味だとされていたことです。人類の先祖は羊の肉を食用に毛や皮は衣類として利用させていただいててきたというわけです。しかし、羊もまた人間様に家畜とされたおかげで弱い生き物ながら、これまで長く生き延び種を増やしてきたとも言えます。
さて、羊という文字が象形文字であることはよく知られていることですが、「羊」を部首にした漢字を上げてみます。「美・養・翔・善・着・義・羨」良い感じのものが多いです。この漢字のような良い年にしたものです。
追加
ところで、これまでのように私の子どもの頃を振り返ってみると、羊はメンヨウ(綿羊)と呼ばれていました。しかし、そうたくさんは飼われていず、私の田舎では代わって山羊を飼っていました。
山羊は子どもでもあやすことができ、山間地の斜面などでも、山羊の首を縄で結わえ、その先を切り株などに結わえ付けておくだけで勝手に草を食、成長してくれたものです。そして、小山羊を生んだ後はお乳を私どもに恵んでくれたというわけです。四足を小さな杭に縛ったあと、お乳をつかみ、右手と左手を交互に握って搾ると、シュウシュウと音がして地面い置いた容器の中にたまったものです。そして、牛乳代わりに飲んだものです。するとウンコが山羊のウンコのようにコロンコロンとしたもになってでたりしてきました。
山羊もも飼育しやすいことが幸いして人間に飼われ、種を増やしてきたものと想像します。しかし、最近は、とんと姿が見られなくなったのが寂しい。頭数? 十年程前に山形県境の小国町のの飯豊山荘に行ったときに、実物に有ったのが最後かな、三匹の小山羊でたいそう可愛かったのが忘れられません。
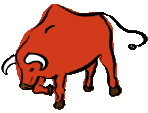
 「さっそうと生きよう 虎のように」 (平成10年)
「さっそうと生きよう 虎のように」 (平成10年) 
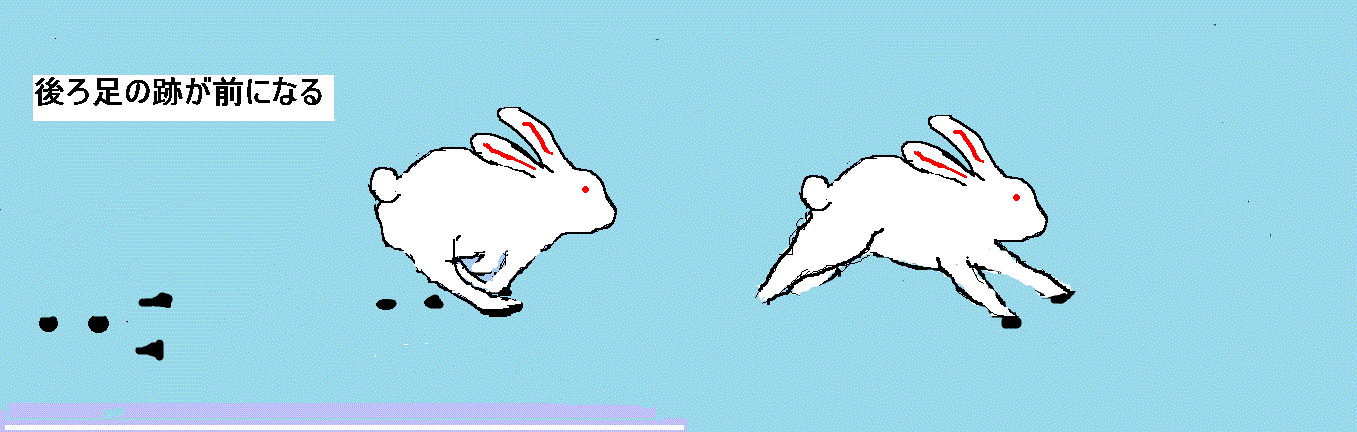
 「龍の気」
(平成12年) 与えられた文字数が この年より減。
「龍の気」
(平成12年) 与えられた文字数が この年より減。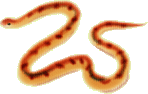 「一皮剥けよう、蛇年」(平成13年)
「一皮剥けよう、蛇年」(平成13年)



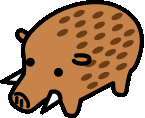
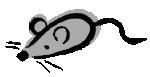 ねずみにちなんだ問題はいかが?(平成20年)
ねずみにちなんだ問題はいかが?(平成20年)