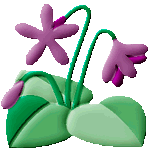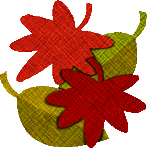元へ戻る 立像転倒のおそれには? (平成22年)
今、奈良の仏像展が長岡で開催されています。それに先立つ4月の上旬、平城遷都千三百の奈良の見物に行きました。その見物の際、お寺の展示、分けても立像は地震で倒れたらどうなるものかと気になりました。以前、長岡の歴史民俗資料館で展示されている縄文式土器類をみて、こんなに宙に浮かせてまで展示したら、地震の際に揺れてぶつかったり、落ちたりしないかと心配していたが、小心ゆえに黙っていたら、その年に地震があって多くの土器が壊れてしまいました。
そんな経験があったので、今回は唐招提寺の特別展示館を見学した際に係の方に地震により倒壊する心配はないかとお聞きしましたところ、「阪神大震災では、震度5でも大丈夫でした。」という返答が返ってきました。高校生のころ、震度7を経験した小生としては、その返答には、いささか異論もあったのですが、小心者ゆえに、またまた「そうですか」と引き下がってしまいました。が、内心は今も心配はしています。
今回、長岡の展示会にも、いくつかの立像が来ていると聞いております。この方はどうなっているのかと気になって公の場を通して尋ねてみたくなりました。先の新潟市民美術館でのカビ発生の事件の後でもあり、より慎重に展示されていますようにと願いつつ、お尋ねする次第です。
(投書せず)
トキがテンに襲われないか(平成22年)
ケージの中のトキがテンに襲われ、痛ましい結果となりました。今、また、野生復帰のトキの卵の孵化が期待されているところでありますが、気がかりなことを申し述べます。
監視や見学は500m離れたところから行うなど、気を配っておられるようですが、また、テンに襲われないないように、ネズミ返しならぬテン返しを作って、木を登ってくる天敵に備えたらどうかと思います。素人考えで恐縮ですが、蛇、テン、猿などから守るための大きなネズミ返しを地上2m程のところに設置したらどうかと思います。
小学生の頃、サシバの幼鳥を捕まえ、育てたことがありますが、サシバは他の地面からは天敵が登れない太いブナの木の高所に巣を架けていたものです。今回のトキはどんな木に巣を架けたのかしらないものが余計な口出しかも知れませんが、立像の転倒と同様に心配で投書してみました。(投書せず)
「プロとアマの違い」(平成8年)
最近はスポーツ界に見られるように、プロとアマの垣根が取り払われつつあります。中学生の皆さんにも何らかの道を選び、その道のプロを目指していただきたいのですが、どうしたらいいか。
プロと呼ばれる人も最初からプロだったわけではありません。プロとはアマチュアを続け続けた人のことだと思います。最初は、アマと呼ばれてもよい、自分の好きなことをやり抜くことが大切です。
若い頃には、どんどん先を行く友達や同級生のことが気になるものです。しかし、自分の努力はいつかどこかで報われる。そう考えて生活しましょう。どんな高い山も、日数さえかければ必ず登れるものです。あわてず、一歩一歩自分の道を進みましょう。
98ノートNS/Eとともに(平成7年) 
コンピュータに強い興味をもったのは七年ほど前、アメリカの中学校を見学したときです。私の訪ねたフロリダの学校では、南アメリカからの難民の子供達が英語を学習するのに、コンピュータを利用していました。英語の発音をイヤホンで聞いて、そのスペルを英語でコンピュータに打ち込む、それが正しければ、「Y」で次へ進むというシステムでした。なるほどこんな使い方もできるのかと感心しました。これは、小さな教育革命だななんて思ったのです。
そして、その年に買ったのがこの98ノートNS/Eです。ほとんど、ワープロとしか使っていませんが、使いながら、愛着が涌いてきて、今では私の無くてはならないパートナーとなりました。記録の苦手なわたしですが、私のいろんなことを記憶しているので、もう一人の私と言った方がよいかもしれません。
どこが似ているのか、似ている点を列挙してみますと。
(1)「心臓がある」 心臓のように常に動いているところがあって、それが止まれば記憶はすべて消えてしまうのでしょうが、止まったことはありません。この電源はどうなっているのか実はまだ知りません。しかし、購入してからずっと休まずに時を刻んでいます。これが止まった時は、ハードデスクに入っている私の記憶はすべて消えてしまうのだろうと思います。フロッピイに保存はしてありますが・・・
(2)「年ともに体も傷ついている」 人間のボデイにあたる機器の表面も傷つきました。98ノートNS/Eの六年は人間の五十才くらい、ちょうど私の年齢くらいかなと思います。私の体のように、あちこちにしみや傷がついています。
(3)「若い者に追い越される運命である」 バージョンアップと言って、ジュニアが育ち、私も私のパートナーもどんどん若い者に追い越されていきます。
(4)「コンピュータそのものの力はいたって無力である」 コンピュータは優れたソフトがあって初めて威力を発揮します。それは、人間にとっての飛行機や自動車などの機械に似ています。人もパソコンも他の力を利用することでその力を飛躍的に拡大させています。止まれ。思考が少し混乱していますね。こんな話をするつもりはなかったのでした。
そう、飛行機もパソコンもすべて、人間が動かしているのです。だから、とにかく人間がしっかりしなければならない。こう言いたかったのですが、そっちの方向に話しが進みませんでした。
IBM社からは、今年あたりに、現在の四分の一の価格のパソコンが発売されるという。平成八年の年頭にあたり、希望を感じさせる話である。そのときまで、もうしばらくパートナー98ノートNS/Eとともに・・・。
「いいなと思った言葉」
(靴をそろえるのは万国共通かな、などと考えながら・・)
はきものをそろえると心もそろう
心がそろうとはきものもそろう
ぬぐときに そろえておくと
はくとき 心がみだれない
だれかがみだしておいたら
だまってそろえておいてあげよう
そうすればきっと
世の中の人の心もそろうでしょう (禅の雑誌より)
もしもし亀よ
もしもし かめよ かめさんよ
せかいで いちばん おまえほど
そんなに のろい ものはない
なんと おっしゃる うさぎさん(後略)
この話の成り立ちは知らないが、この話の意味するところは、年とともに実感として分かってきました。かめのような生き方の大切さがしみじみと伝わってくるのです。休まずにものごとをやり抜くことの大切さが・・・です。若い頃には、どんどん先を行く友達や同級生のことが気になるものです。
しかし、自分の努力はいつかどこかで報われる。あるいは、歩き続けていれば後退はないと。どんな高い山も、日数さえかければ必ず登れるものです。あわてず、一歩一歩自分の道を進んでいきましょう。
学級(平成6年)
ソビエト社会主義共和国連邦が崩壊しました。学級と国家とを同列に考えるのは少し無理もあるが、この二つは似ている点がたくさんあります。 一つは、人間でもないのにきちんとした名前をもっていて、生きているもののようだということです。一人の人間のように扱われ、人を喜ばせ幸せにするとともに、人を傷つけたりする。そう、生き物のようだということです。もう一つは、自分とは無関係のようで無関係でないところでしょう。国が平和でなくて、どうして個人が幸福であるでしょう。学級が落ち着きがなくて、どうして個人に落ち着きがあるでしょう。私たち人間はいろんな共同生活を営んでいます。毎日の食べ物は、誰かが作ってくれています。その共同社会の一員であることを考えながら、自分の自由や個人の役割を見つめなければならないのです。かのケネデイ大統領は「国家が貴方に何をしてくれるかでなくて、貴方が国家に何ができるかを考えよう」ということを言った。こんなふうに考えて、まずはこの小さな学級での自分の在り方を見つめ直してみましょう。わがままは言わず。
M君のこと(平成5年) 
思い出深い生徒が何人もいる中から、M君の話をします。今でこそサッカーは人気スポーツになりましたが、十年ほど前で、今ほど盛んではなかった頃のことです。ある生徒が高校でサッカーをやりたいので、京都の中学校に転学したいと言ってきました。中学三年生のうちに、その高校のサッカー部の顧問の先生の家に住所を変えてしまわなければならないというのです。その高校が私立の高校なら卒業 後でも良かったのですが、府立高校だったのでそんな手続きが必要だったのです。しかし、彼のいた西蒲原郡の中学校にはサッカー部はなく、彼は陸上部に入っていました。彼の運動能力的な面からも、当時、私は正直のところ、賛成しかねる気持ちでいました。だが、彼は新潟県のふるさとの友達もたくさんいる中学校の卒業を待たずに、私の学級から、三年生の十月頃に転校して行きました。それがM君です。
後でも良かったのですが、府立高校だったのでそんな手続きが必要だったのです。しかし、彼のいた西蒲原郡の中学校にはサッカー部はなく、彼は陸上部に入っていました。彼の運動能力的な面からも、当時、私は正直のところ、賛成しかねる気持ちでいました。だが、彼は新潟県のふるさとの友達もたくさんいる中学校の卒業を待たずに、私の学級から、三年生の十月頃に転校して行きました。それがM君です。
彼がその後、一流のプレイヤーになったかというと、そうではありません。しかし忘れがたい生徒です。私が卒業まで担任した生徒ではないけれども、強く記憶に残り、いつまでも気にかかり、応援を送りたい生徒でした。なぜでしょうか?
平成の時代の中学生の皆さん。このM君のように、何かにぶつかっていく情熱をもって生きてください。周りのものが、なぜか応援したくなるような夢をもって、自分で切り開いて行ってください。若いうちには、何も怖さを感じないそんな元気な時期があります。頑張ってください。最後に、私の好きな言葉を贈ります。
本気でやれば、何でもできる。
本気でやれば、何でもおもしろい。
本気でやれば、誰かが助けてくれる。
山野草の四季(平成4年)
私は春が来ると、山にいきたくなります。自分なりに考えてみると、山には、植物がいっぱいあって、みんな「いらっしゃい」と言って、私を歓迎してくれるからだと思います。春の野は、かたくり、雪割草、一輪草の花が、みんな「私を見て下さい」「きれいでしょう」と口々に、自慢しているように見えます。「ああきれいだね」と言うと心から喜んでくれ、「また来年も逢いに来てね」って言ってくれます。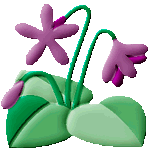
夏の林の中は、樹木の葉から発するオゾンがいっぱいで、人間の健康に良い影響を与えると言われています。また、大木には幹が発散する殺菌作用があって、それが人間の体にも良い影響を与えるそうです。大きなブナの林の中にいると、本当に、そんな感じが伝わってくるようで、思わず木を抱きしめたくなります。そして、たとえ、相手がブナの木であっても、愛情のようなものを感じます。ブナの木のおだやかで、おおらかなやさしさに包まれ、自分を大事にしていただいているという安心感にひたれます。
秋は、またたびの実、あけびの実、やま葡萄の実などなが、食を豊かな楽しいものにしてくれます。自然のものは、ことさら「いただきます」という感謝の気持ちでたべます。
初冬に近い十二月、雪も降らなかったので、私は近くの山に登りました。何にも無いかのような林の中です。かさかさと落ち葉を踏みしめて山を登っていました。人気の無さにさびしい思いでいました。ところが、ふと見ると、いたんですね。目の高さのところに、とんがった芽の先を向けて・・・。何千何万というたくさんの木の芽が、じっと息をころすようにして、来春の準備をしていました。たくさんの命の仲間がいたのです。山の草木も、一時として休んでいるわけではなかったのです。次の年の生活に向けてじっと力をたくわえている人間のようです。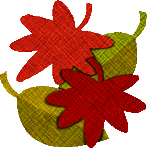
こんな植物を育てていると、ああ、人間に似ているなと思うことがしばしばあります。明るい太陽の下を好むもの、日陰を好むものもあります。湿り気のある所を好むもの、そうでないものもあります。だから、家の周りのどこにどの植物を植えるかは、その植物とよく相談して決めています。ふさわしい環境を得た植物は自力で何の手入れもなくとも、ぐんぐんと自力で成長してゆきます。そして、いつの間にか大きくなっていて喜ばせたりします。
平成5年の春がまたやってきます。植物のように、自分の適性にあったところでのびのび力いっぱい生きたいものですね。


 後でも良かったのですが、府立高校だったのでそんな手続きが必要だったのです。しかし、彼のいた西蒲原郡の中学校にはサッカー部はなく、彼は陸上部に入っていました。彼の運動能力的な面からも、当時、私は正直のところ、賛成しかねる気持ちでいました。だが、彼は新潟県のふるさとの友達もたくさんいる中学校の卒業を待たずに、私の学級から、三年生の十月頃に転校して行きました。それがM君です。
後でも良かったのですが、府立高校だったのでそんな手続きが必要だったのです。しかし、彼のいた西蒲原郡の中学校にはサッカー部はなく、彼は陸上部に入っていました。彼の運動能力的な面からも、当時、私は正直のところ、賛成しかねる気持ちでいました。だが、彼は新潟県のふるさとの友達もたくさんいる中学校の卒業を待たずに、私の学級から、三年生の十月頃に転校して行きました。それがM君です。